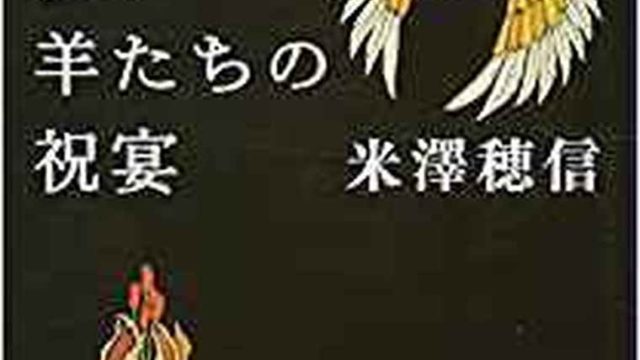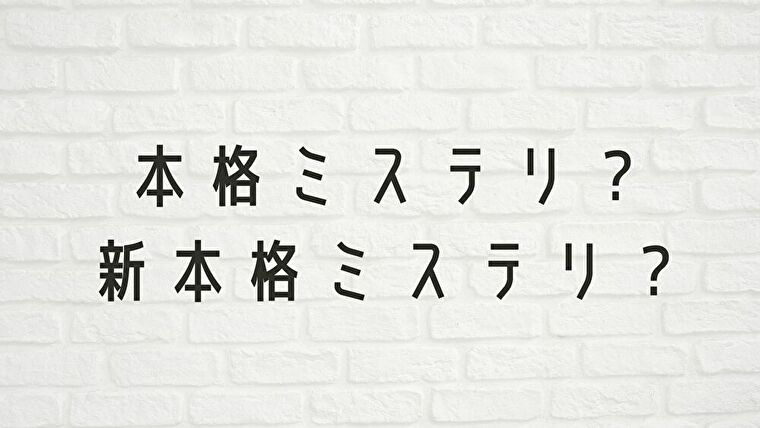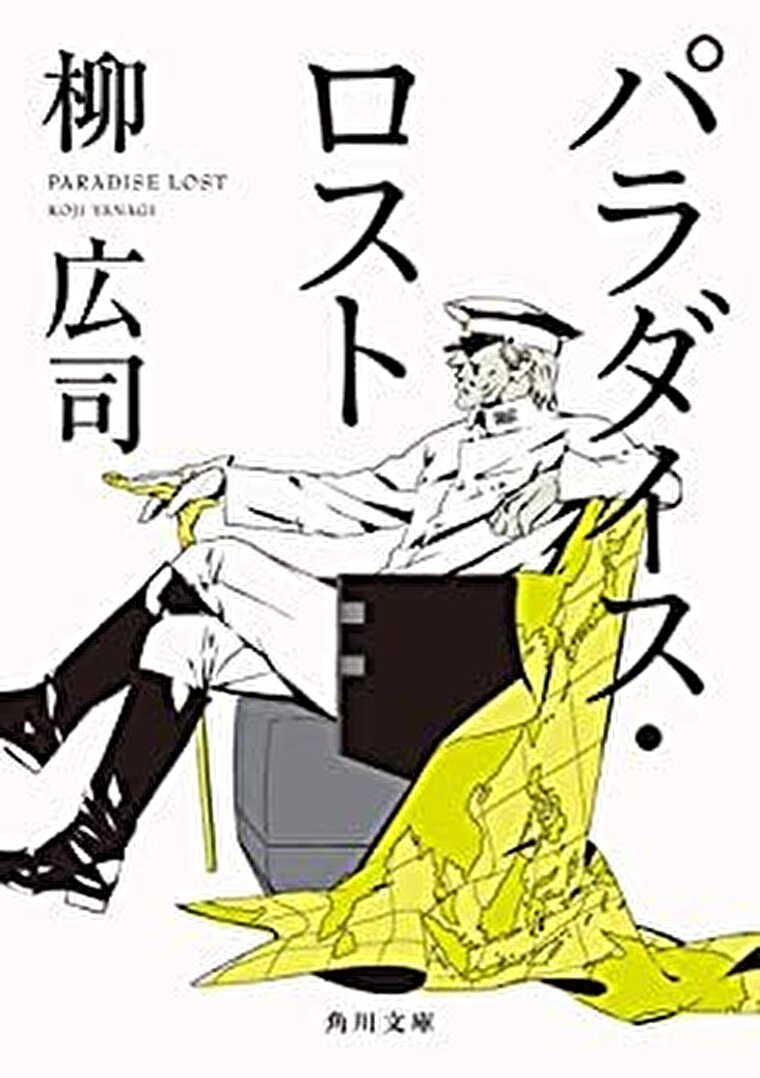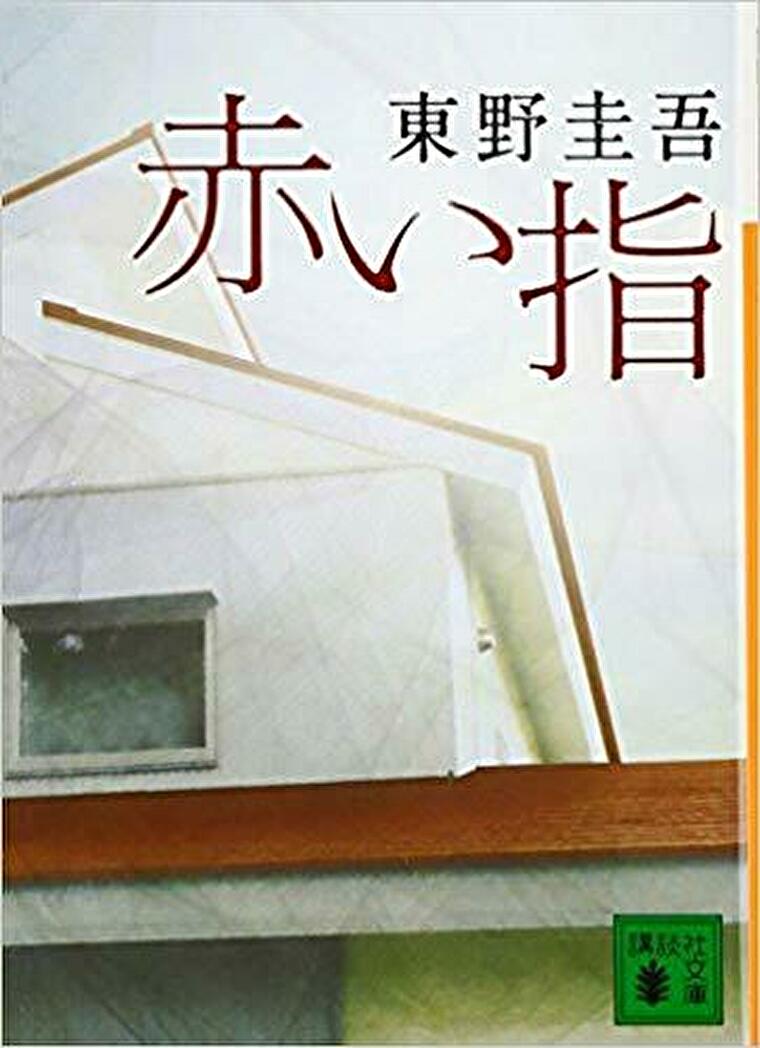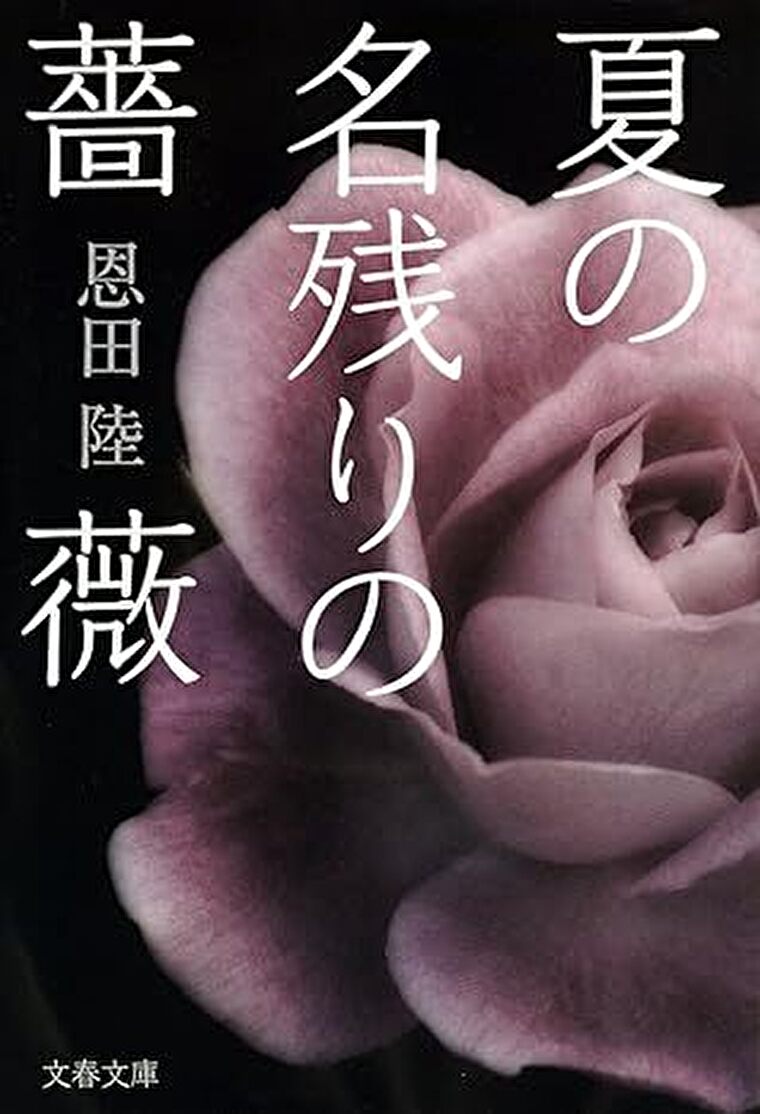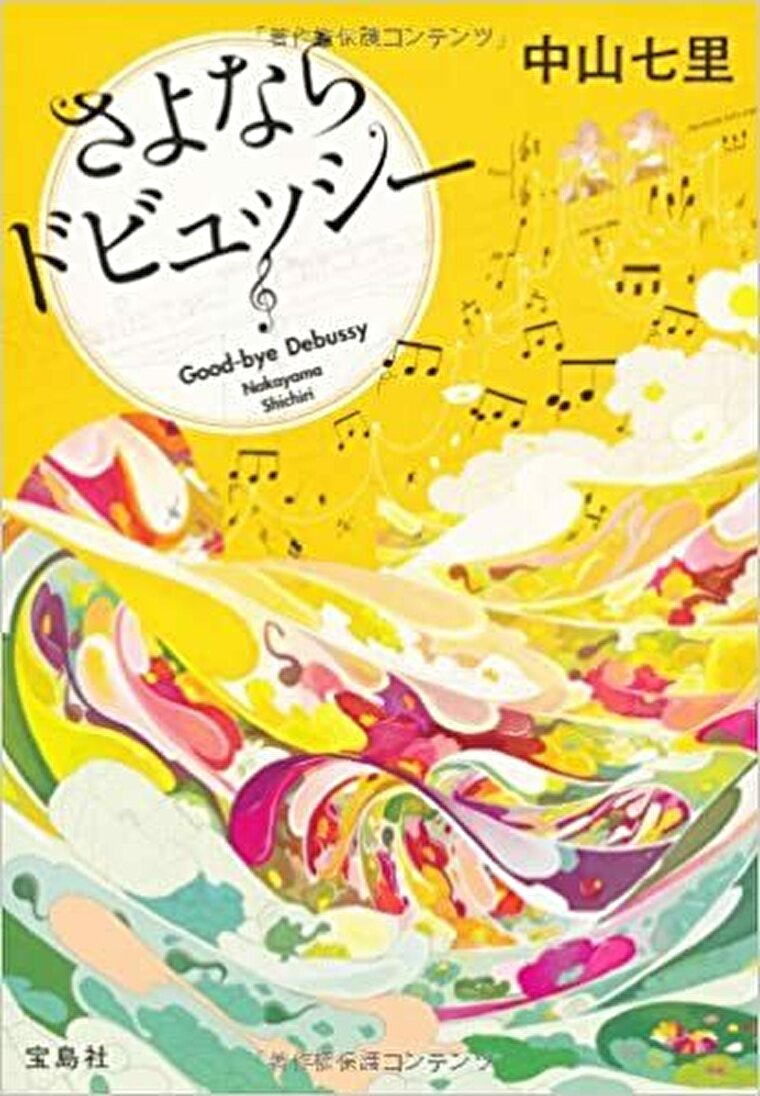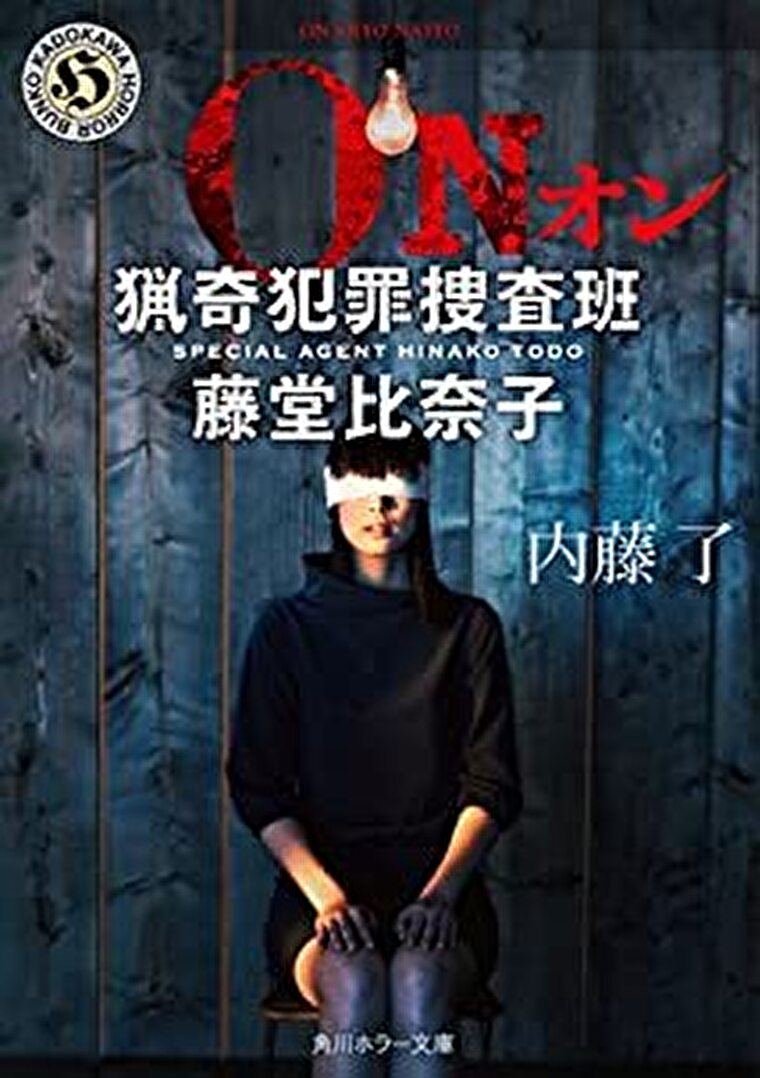『さよなら妖精』あらすじとネタバレ感想!異国の少女との不思議な日々と残された謎
一九九一年四月。雨宿りをする一人の少女との偶然の出会いが、謎に満ちた日々への扉を開けた。遠い国からはるばるおれたちの街にやって来た少女、マーヤ。彼女と過ごす、謎に満ちた日常。そして彼女が帰国したとき、おれたちの最大の謎解きが始まる。覗き込んでくる目、カールがかった黒髪、白い首筋、『哲学的意味がありますか?』、そして紫陽花。謎を解く鍵は記憶の中に――。忘れ難い余韻をもたらす、出会いと祈りの物語。著者の出世作となった清新なボーイ・ミーツ・ガール・ミステリ。
Amazon商品ページより
『ベルーフ』シリーズの一作目となる本書。
異国の少女と運命的な出会いを果たし、彼女と忘れられない青春を過ごす。
それだけであればボーイ・ミーツ・ガールとして青春、恋愛小説として分類できますが、本書はまぎれもなくミステリです。
その所以は、少女が帰国した後に残された謎にあります。
このほろ苦さが米澤穂信さんならではで、必読の一冊です。
この記事では、本書のあらすじや個人的な感想を書いています。
核心部のネタバレは避けますが、未読の方はご注意ください。
本をお得に読みたい人には『Kindle Unlimited』をオススメします。
小説のみならずビジネス書、マンガ、専門書など様々なジャンルの作品が500万冊以上読み放題。
新規加入なら30日間の無料体験ができるので、無料期間中に退会すればお金は一切かかりません。
なかなか手に取れない数千円、数万円するような本を読むのもアリ。
マンガであれば一か月で数十冊読めてしまうので、シリーズものも無料で読破できます。
気になる人はぜひ30日間無料体験でお試しください。
あらすじ
本書は過去と現在が交互に描かれ、当時の状況を思い出しながら謎に挑む、という構成になっています。
出会い
1991年4月。
高校三年生の守屋路行と太刀洗万智は下校時、雨宿りする少女を見つけます。
黒い髪に大きなバッグ。
外国の旅行者のように見えます。
二人が声を掛けると少女はマーヤと名乗り、それなりに流暢な日本語で父親の仕事の関係でユーゴスラヴィアから日本に来たことを教えてくれます。
滞在期間は二か月間で、父親の友人の家に滞在するつもりでこの街に来ました。
ところがその人はすでに亡くなっており、日本にいる間はマーヤは父親と別行動することがルールになっていて頼ることはできません。
守屋と万智が考えた結果、友人で家が旅館を経営する白河いずるを頼ることにし、マーヤはいずるの家に住まわせてもらうことになりました。
日常に潜む謎
ここからマーヤとの日々が始まります。
上述した三人に守屋と同じ弓道部の文原竹彦を加え、五人で色々な経験をします。
そこまで大したことはしていないつもりでも、マーヤにとってはじめてのことばかりで、彼女を目を通すとそこにはたくさんの謎が隠されていました。
最大の謎
マーヤの帰国後、大学生になった守屋たちが描かれます。
マーヤの住むユーゴスラヴィアでは武力衝突が起こり、とても危険な状況にありました。
守屋は彼女のことを助けたいと思いますが、ここで大きな問題があります。
それはユーゴスラヴィアとは特定の国の名前ではなく、六つの国の集まりだったからです。
守屋たちはマーヤと過ごした日々を思い出し、彼女の言葉の中に散りばめられたヒントをかき集め、彼女の住む国を掴もうと努力していました。
安全な国でありますように。
そう願う中、ついにマーヤの住む国が明らかになります。
感想
忘れられない青春
マーヤの国で起こる戦争のことが合間合間に描かれるため、青春小説と言い切ってしまうには重く、苦い内容です。
しかし、それでもマーヤと過ごす日々は読んでいて本当に瑞々しく、まさに青春そのものでした。
マーヤの魅力はもちろんのこと、守屋たち四人のバランスも素晴らしいです。
実は米澤さんの『愚者のエンドロール』が出た後、レーベルが休止になることで古典部シリーズが続けられなくなったことがありました。
その時に出来ていた原稿があり、どうしても出版したいという意向から改稿され、古典部シリーズでない本書として出版された経緯があります。
そのせいか古典部シリーズとベルーフシリーズの登場人物には似ているところがあり、古典部シリーズの面影を本書に見るのは面白かったです。
詳しくは以下のインタビュー記事をご覧ください。
なぜ〈古典部〉シリーズの『愚者のエンドロール』の次に『さよなら妖精』を書いたのか――米澤穂信(2)|文春オンライン
無力感
高校時代の描写は鮮やかで楽しいひと時でした。
しかし、大学時代の描写で終始重苦しくのしかかるのは『無力感』です。
これまでのヒントからマーヤのいる国を当てることは難しい。
かつ分かったところで、守屋たち一学生に出来ることなどありはしない。
特に守屋は周囲の声を押しのけてでもマーヤの居場所を掴もうとしますが、分かったところで自分に何もできないことくらい分かっています。
それでも探さずにはいられない。
このやり場のない気持ちが痛々しく、それも含めて本書は良質な青春ミステリでした。
おわりに
米澤さんというとどうしても古典部シリーズが思い浮かびがちですが、僕は本書も米澤さんの代表作としてぜひ読んでほしいと思います。
何回読んでも心が締め付けられるし、時間が経つと求めずにはいられないほどの名作です。
ベルーフシリーズ第二弾はこちら。

本をお得に読みたい人には『Kindle Unlimited』をオススメします。
小説のみならずビジネス書、マンガ、専門書など様々なジャンルの作品が500万冊以上読み放題。
新規加入なら30日間の無料体験ができるので、無料期間中に退会すればお金は一切かかりません。
なかなか手に取れない数千円、数万円するような本を読むのもアリ。
マンガであれば一か月で数十冊読めてしまうので、シリーズものも無料で読破できます。
気になる人はぜひ30日間無料体験でお試しください。
米澤さんの他の作品に関する記事はこちら。
関連記事はこちら。