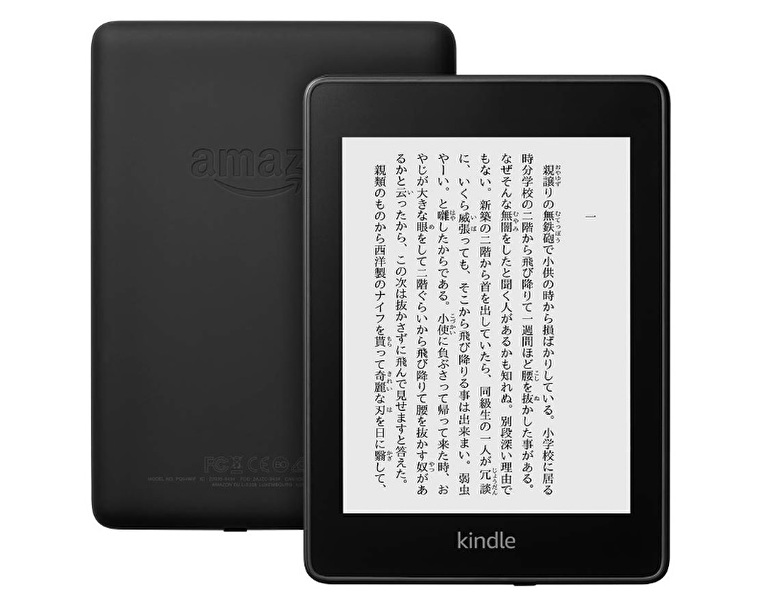宮部みゆきの作品は電子書籍化されている?電子書籍市場の現状を解説!
宮部みゆきさんといえば超有名作家で、電子書籍化されていれば読者にとってより手に入れやすいことになります。
ところが、宮部さんは一部作品をのぞいて電子書籍化を認めていないことが分かりました。
Kindle などサービスによる差はなく、作品ごとに判断しているようです。
有名どころでいうとブレイブストーリーなどがあり、10作品程度。
宮部さんのキャリアを考えると、ごく一部であることが分かります。
この記事では、その理由について解説していきたいと思います。
本をお得に読みたい人には『Kindle Unlimited』をオススメします。
小説のみならずビジネス書、マンガ、専門書など様々なジャンルの作品が500万冊以上読み放題。
新規加入なら30日間の無料体験ができるので、無料期間中に退会すればお金は一切かかりません。
なかなか手に取れない数千円、数万円するような本を読むのもアリ。
マンガであれば30日で数十冊読めてしまうので、シリーズものも無料で読破できます。
気になる人はぜひ30日間無料体験でお試しください。
そもそも誰に決定権があるのか
本題に入る前に、一体誰に電子書籍化を決める権限があるのか。
これは基本的にその本を書いた作家自身だといわれています。
なので、宮部みゆきの作品の電子書籍化を許可しない=宮部みゆき自身の意思だと思って構わないと思います。
宮部みゆきが電子書籍化を許可しない理由
肝心の本題ですが、その理由が明記されているものを見つけられませんでした。
しかし、以下の記事から宮部さんのスタンスが見えてきました。
決して電子書籍を否定しているわけではなく、紙の本とうまく住み分けることを願っているのが分かります。
しかし、紙の本を愛し、出版文化を守りたいという思いも強いことがよく分かり、自身の作品を電子書籍化しないのはそういった点が理由になっているのかもしれません。
あと宮部さんほどのキャリアがあれば電子書籍化しなくても困らなそうなので、今後もよっぽどの理由がない限り、電子書籍作品の追加は期待薄な気がします。
おわりに
宮部さんはブレイブストーリーなど一部作品をのぞいて電子書籍化を認めていません。
そこには出版業界、読者双方にとってよりより未来を目指す宮部さんの思いが込められています。
そのことを考えると、よっぽど事情が変わらない限り、新たな作品の電子書籍化は難しい気がします。
僕としては市場を買い支えたい一心なので、媒体限らず良い作品であれば絶対に買います。
もちろん、電子書籍も利用していますので、今以上に作品が増えるのは大歓迎です。
本をお得に読みたい人には『Kindle Unlimited』をオススメします。
小説のみならずビジネス書、マンガ、専門書など様々なジャンルの作品が500万冊以上読み放題。
新規加入なら30日間の無料体験ができるので、無料期間中に退会すればお金は一切かかりません。
なかなか手に取れない数千円、数万円するような本を読むのもアリ。
マンガであれば30日で数十冊読めてしまうので、シリーズものも無料で読破できます。
気になる人はぜひ30日間無料体験でお試しください。