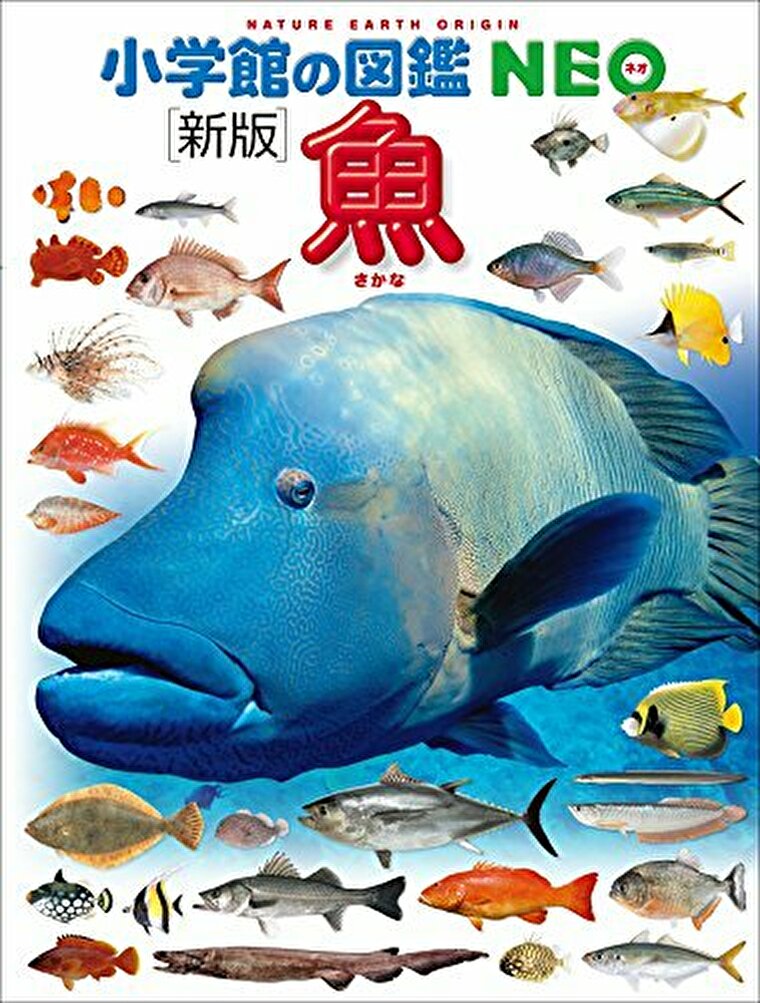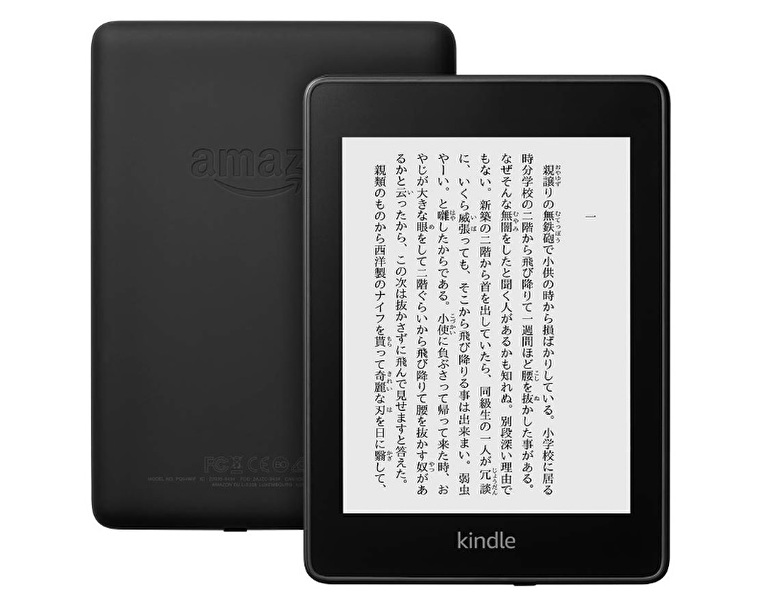電子書籍が売れない8つの理由!紙の本の需要はまだまだある?
今ではすっかり市民権を獲得している電子書籍。
僕も気が付けば日常的にお世話になっていますが、ここで常に考えていたことがあります。
それは『いずれ紙の本は無くなってしまうのか?』という疑問です。
スマホの普及、紙資源の枯渇、置き場所や手軽さなど利便性の問題。紙の本にとって逆風なのは間違いありません。
それを証明するかのように、街の本屋さんがつぶれ、印刷業界が大変だなんてことも耳にします。
しかし実際は売上こそ減少していますが、電子書籍に比べて紙の本の方が売れているのが現状です。
そこで今回は、電子書籍の売上推移から今後の本の在り方について書いています。
※2024年1月25日時点でのデータをもとに解説しています。
本をお得に読みたい人には『Kindle Unlimited』をオススメします。
小説のみならずビジネス書、マンガ、専門書など様々なジャンルの作品が200万冊以上読み放題。
新規加入なら30日間の無料体験ができるので、無料期間中に退会すればお金は一切かかりません。
また期間限定で2か月1,960円→99円の破格なプランもあります。
なかなか手に取れない数千円、数万円するような本を読むのもアリ。
マンガであれば一か月で数十冊読めてしまうので、シリーズものも無料で読破できます。
気になる人はぜひ30日間無料体験でお試しください。
電子書籍の売上推移
まず参考にしたのが以下のページ。
2023年出版市場(紙+電子)は1兆5963億円で前年比2.1%減、コロナ前の2019年比では3.4%増 ~ 出版科学研究所調べ
このページを見ると、2023年の出版物(紙の書籍と雑誌の合計)は前年比6.0%減、電子出版市場は前年比6.7%増となり、紙と電子を合算した全体の市場は前年比2.1%減の1兆5,963億円となりました。
電子書籍は変わらず伸びているものの、出版市場としては縮小傾向が続いています。
町の本屋が次々と閉店に追いやられている現状を見ると、自分の体感ともズレていないかなと思います。
市場自体は若干の縮小ですが、比率は電子書籍がさらに増えており、これではいずれ紙の本を見なくなる日がくるというのも、あながち冗談とは言えないかもしれません。
ただ紙の本から電子書籍にシフトしているようにも見えますが、それはあくまでコミックくらいで、電子書籍や電子雑誌なんて微々たるものです。
つまり、電子書籍はまだそこまで浸透していないということになります。
それはなぜでしょうか?
自分なりにその理由を考えてみました。
電子書籍が売れない8つの理由
① 電子書籍を読むには端末が必要
当たり前のことですが、電子書籍を読むには専用端末やスマホが必要になります。
スマホであればかなり普及していると思われますが、実際はどうなんでしょうか?
参考にした記事はこちら。
スマートフォンとタブレット型端末の普及率の推移をさぐる(2020年公開版)
今後、ガラケーもどんどんサービスを終了することが予想されるので、この点については以前ほど普及の妨げになっていないと思われます。
② 本の質感に及ばない
技術的な問題で、実際に本をめくる時の感触に近づけようと日々改良が加えられていますが、まだ紙の本には及びません。
また紙であればペンで線を引く、印をつけるなど誰でもできますが、電子書籍だと端末を使いこなせないとこんな当たり前のこともできません。
わざわざ使い方を調べるくらいなら、紙の本で良いと思ってしまっても仕方がないのかもしれません。
慣れ親しんだ習慣を変えるというのは簡単なことではありません。
ただし、電子書籍は日々進化しています。
僕はKindle ペーパーホワイトを購入して電子書籍を読んでいますが、紙の本とは違った魅力が詰まっていました。
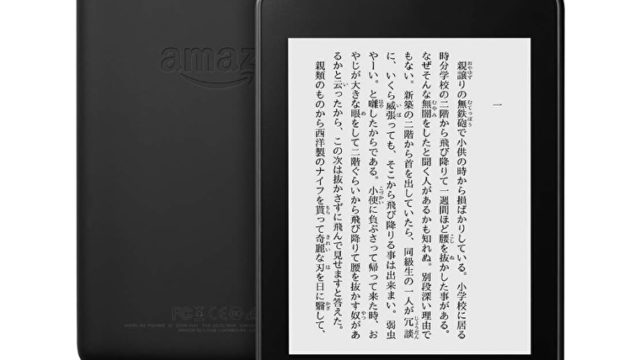
比べるのではなく、それぞれの良さに目を向けると読書がより豊かになると思います。
③ 内容を覚えられない
衝撃的な内容ですが、ノルウェー・スタヴァンゲル大学のAnne Mangen氏の研究報告によると、従来の書籍を読んだグループに比べて、電子書籍を読んだグループの方が内容を覚えていないことが明らかになりました。
電子書籍より紙の本で読んだほうが、内容をよく記憶できる:研究結果
登場人物やストーリーなど基本的な部分は同等の正解レベルでしたが、より詳しい内容に入ると明らかに電子書籍を読んだグループの方が記憶していないとのことです。
理由として、本の重さや手触り、紙の匂いなどが刺激となり、脳の活動が活発になるからだと考えられています。
今の学校では電子端末が黒板、ノートなどに取って変わっているというニュースも見かけますので、その影響が今後出てくるのかもしれません。
④ 価格が高い
え、電子書籍の方が安いじゃん、と思われた方も多いと思います。
確かに新品の本に比べると、電子書籍は多少安く、またキャンペーンを行っていれば格段に安く購入できます。
しかし、これはあくまで新品の話であって、中古本であれば、紙媒体であれば下手したら数円から数十円で購入できてしまいます。
最近はネットで買うと送料でかなりとられるので、実際はもっとかかりますが、それでも格段に安いです。
ところが、電子書籍に中古という概念はありませんので、ここまで極端な値段で販売されることはありません。
読めれば良いという方であれば、迷わず中古本を選ぶでしょう。
また電子書籍は売ることもできませんので、読んだ本を売って次の本の費用の足しに、なんてことも出来ません。
利便性の高い電子書籍ではありますが、このように融通のききづらい一面もあります。
ただし、著者の利益になるのは新品だけなので、今後の活動を応援するという意味では新品を買った方が良いともいえます。
⑤ 売れない
電子書籍は購入後、当然ですが売ることはできません。
一方で、紙の本は購入後、売ることが出来ますので、売ったお金を次の本を購入する原資に充てることが出来ます。
この項目を書くにあたって、非常に興味深かったのが以下の記事。
「読み終えたら即メルカリ」は許せない? 中古売買は電子書籍にはない紙媒体の長所
この記事では売れるという点を紙の本に捉えていて、実際、下取りが可能だと購買意欲を増すそうです。
読んですぐに売られてしまうと著者としては悲しいかもしれませんが、この紙の本のメリットを前面に出すことで販売部数が伸びるのであれば、決して悪いことだけではないのかもしれません。
⑥ 電子書籍に関する情報が入ってこない
紙の本であれば本屋にずらっと並んでいるので、それを見れば今の流行り、売れ筋などすぐに分かります。
また出版社別、ジャンル別に並んでいるので、直感的に自分の欲しい本を選ぶことが出来ます。
しかし電子書籍の場合、ストアを見ても一覧として出てくるのはごく一部で、自分で検索する必要があります。
購入する本が決まっていれば非常に便利ですが、なんとなく良い本がないか探す方には一苦労かもしれません。
ただ一方で、購入した本から近いジャンルの本などをおすすめしてくれるので、自分好みの本が見つかりやすいという利点もあります。
この項目に関しては、まだ改善がしやすいようにも感じますし、うまくすれば紙の本を大きく上回る利点になりそうです。
⑦現物主義
特に上の年代の方ほど多いと思いますが、手元に現物であるから安心でき、データだとなんとなく不安になってしまうという状況です。
こればかりは育ってきた環境の問題なので、どれだけ説明しても理解が得られないかもしれません。
またコレクションとして飾る楽しみも紙の本であれば出来るので、様々な欲求をまとめて満たすにはまだまだ紙の本が優勢でしょう。
僕もその一人で、電子書籍も以前に比べればよく購入するようになりましたが、まだまだ紙の本に愛着があります。
⑧独特な日本の出版流通
僕がこの記事を書いていて一番面白いと感じたのが以下の記事。
書籍は出版社から取次を通して書店に並べられますが、あくまで『委託販売』という形式であり、一定期間売れなければ出版社に返本することができます。
出版社としてはなるべく返本を避けたいので、初動売上を書籍の増刷、連載の打ち切りの指標とします。
ところが電子書籍にはそもそも在庫という概念がないので、返本を気にする必要がありません。
するとますます書籍に力が入り、結果として今でも紙媒体での売上が重要視されているというわけです。
読者ではなく出版流通側の問題なので、なんとかならないのかと思う一方で、様々な企業の命運がかかっているのかと思うと、仕方がないと諦めてしまう気持ちにもなります。
ただこの業界に限らず、昔のシステムをいつまでも維持・発展していけるわけではないので、そろそろ問題から目をそらさず、ちゃんと向き合う必要があるのかもしれません。
おわりに
この記事を書いていて、確かに紙の本と電子書籍の市場は大きく重なっていますが、決して全て置き換えることはできないと考えるようになりました。
紙の本の良さがあれば、電子書籍の良さもある。
出版業界自体、厳しい状況に置かれていることは間違いないので、両者が手と手を取り合ってより業界として発展することを祈っています。
本をお得に読みたい人には『Kindle Unlimited』をオススメします。
小説のみならずビジネス書、マンガ、専門書など様々なジャンルの作品が200万冊以上読み放題。
新規加入なら30日間の無料体験ができるので、無料期間中に退会すればお金は一切かかりません。
また期間限定で2か月1,960円→99円の破格なプランもあります。
なかなか手に取れない数千円、数万円するような本を読むのもアリ。
マンガであれば一か月で数十冊読めてしまうので、シリーズものも無料で読破できます。
気になる人はぜひ30日間無料体験でお試しください。